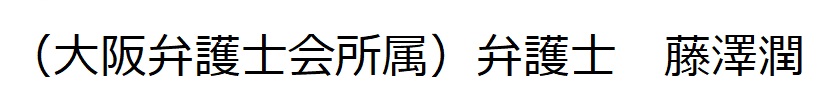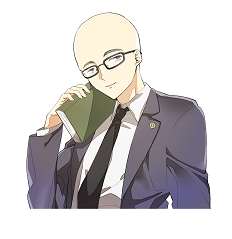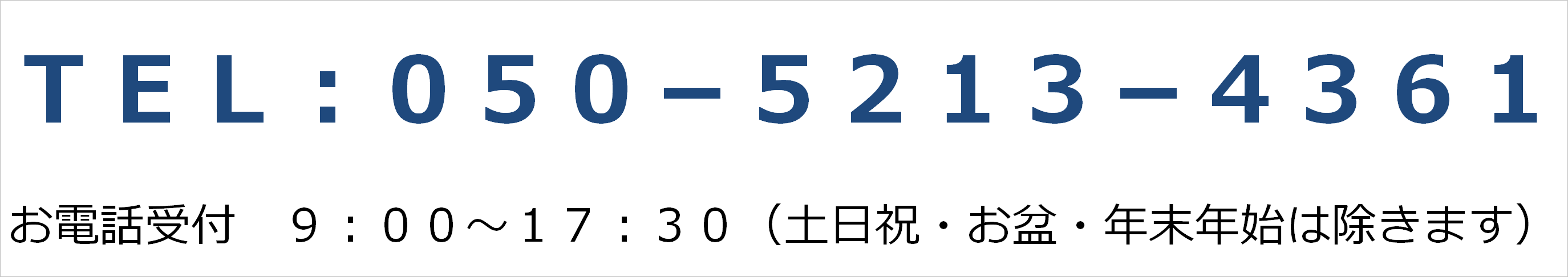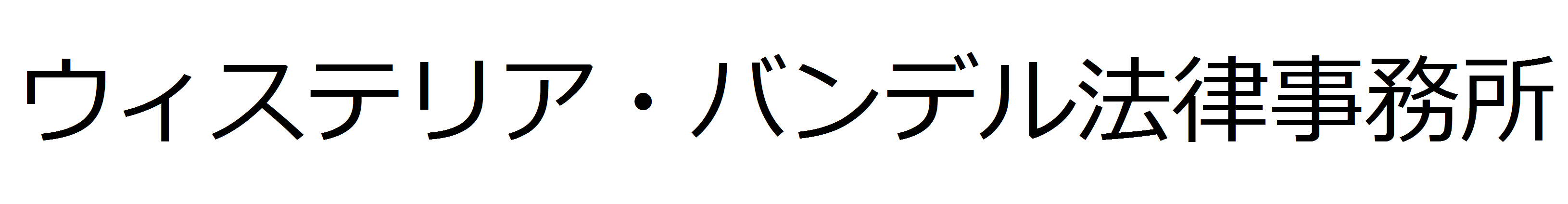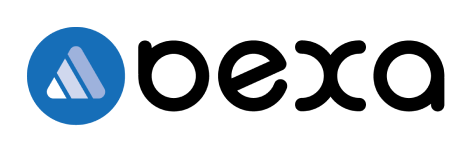はじめに
ウィステリア・バンデル法律事務所では、インターネット(5ch、ツイッター等)にかかる誹謗・中傷・プライバシー侵害等(いわゆる炎上など)のご相談を多くいただいています。その多くは「犯人を特定して謝罪させたい」「慰謝料請求したい」というものですが、当事務所でインターネットの誹謗中傷について、どのように考えているのかご説明しようかと思います(なお、削除請求も並行して行うことも多いです)。
犯人特定のためには

法的責任を追及するためには「犯人特定」をしなければなりません。犯人特定の手法として、「発信者情報開示請求」というものがあります。発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿者を特定するための法的手続をさします。インターネットは匿名で書き込みがされることが多いため、名誉毀損やプライバシー侵害といった違法な書き込みをした者に対して、損害賠償請求や刑事告訴をするためにまず発信者情報開示請求という手続を採る必要があります。
発信者情報開示請求の根拠は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律にあり、一般的には情報流通プラットフォーム対処法とよばれます(以下、「情プラ法」とします)にあります。詳細は省略しますが、情プラ法第5条第1項の要件を満たした場合に発信者情報開示請求をすることができます。なお、メールやツイッターのメッセージ等、特定個人間の誹謗中傷等は情プラ法第2条第1号の「特定電気通信」にあたらないため、発信者情報開示請求をすることはできません。この場合、任意開示や弁護士会照会(弁護士法第23条の2。「23条照会」ということもあります)などといった方法をとることになります(写真は兵庫県養父市)。
なお、たとえ弁護士に依頼したとしても、犯人特定に失敗する可能性はあります(「〇〇すれば、確実に特定できる」「100%特定可能」などといううたい文句には注意してください)。
発信者情報開示請求手続の流れ
おおまかには、以下の流れとなります。
1-1.コンテンツプロバイダに対して、投稿者のIPアドレス・タイムスタンプ等の開示請求をします。
コンテンツプロバイダ(Contents Provider、以下「CP」とします)とは、インターネット接続サービス事業者をいい、Twitter(現:X。以下、Twitterとします)やGoogleなどがこれにあたります。まず、氏名登録型サイトでもない限り、CPが氏名・住所等を保有していることはないので、CPに対してIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めることになります(IPアドレスとタイムスタンプの詳細な説明は省略します)。任意開示や23条照会で開示に応じるCPもありますが、投稿者の個人情報保護の問題から、これらに応じないCPも少なくありません。その場合、裁判所の仮処分(「ヨ」事件とよばれることがあります)若しくは発信者情報開示命令(「発チ」事件とよばれることがあります)という方法を採ります。どちらを採るかは、CPによって異なるところですが、いずれにしても裁判所の開示決定が得られれば、「公的機関のお墨付きがある」ということで、多くのCPが開示に応じます。ただし、近時は開示決定のみでは開示をしない(開示が遅い)CPも存在することから、開示決定後にさらなる手続を要することがあります。
他方で、投稿者が二段階認証を行っている場合、1-1とは別にあるいは1-1と並行して、CPに電話番号の開示を求めることができます。この場合、1-2・1-3を省略して、電話番号から23条照会などを利用して特定することができることがあります。電話番号の開示は、通常保全の必要性が認められないため、仮処分ではなく発信者情報開示命令手続を行うことになります。
いずれの手続も、法的に権利侵害といえる場合(細かな要件はここでは割愛します)のみ開示が認められます。特に、「誹謗中傷」の場合、法的権利侵害にあたらないケースも少なくないので、後述の技術的問題や手続の複雑さ以前に、裁判所で開示が認められないことも少なくありません。
1-2.1-1で得られた情報をもとに投稿者のインターネットサービスプロバイダを特定します。
インターネットサービスプロバイダ(Internet Service Provider,以下、「ISP」とします。なお、AP(Access Provider)と呼ぶこともあります)とは、インターネット接続事業者のことをいいます。whoisとは、IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を、インターネットユーザーが誰でも参照できるサービスをいいます。IPアドレスがわかれば、誰でも検索することができます。なお、MVNO(仮想移動体通信事業者,Mobile
Virtual Network Operator)が入ることも多いのですが、かなり細かくなるのでここでは割愛します。
1-3.1-2で判明したインターネットサービスプロバイダに対して、投稿者の住所、氏名等の開示請求を行います。
1-1と同様に投稿者の個人情報保護の観点から、多くは裁判所に対し、ISPを相手方とする発信者情報開示命令手続を採ることになります。これとあわせて、ログ保存手続をとることもあります。なお、上記発信者情報開示命令手続をとる前に、任意開示を求めることがあり、たまに任意開示により開示があることもあります(投稿者が自らの非を認めて和解の申し入れをする場合などです)。また、任意開示に応じない場合であっても、ISPが任意でログ保存を行うことがあります。そのため、裁判手続による発信者情報開示命令手続の申立ての前に、任意開示を求めることも多いです。
発信者情報開示請求の問題点
2-1.成功するかどうかわからない。
要件をみたせば、1-1~1-3の手続で投稿者の特定が可能だと思われる方も少なくありません。しかし、以下のような場合、発信者情報の特定は困難又は不可能となります。特定は可能であっても、調査に時間と費用がかかりますし、成功率も下がります。手続が簡素化したとは新手続のもとでも技術的な問題は残されています。特に近時、裁判所による開示命令発令後、開示に時間がかかるCPが増えていることから、ログ保存期間経過事例が多くなっています。
〇 そもそも、法的に開示要件をみたさない(弁護士の検討段階で意外と多いです)
〇 サイト管理者の住所・氏名等が不明(特にサーバー情報すら不明なことが多いです)
〇 ログ保存期間(通常3~6か月)が経過
〇 IPアドレスとタイムスタンプから、1つの通信に特定できない。
〇 投稿者が街中の無料wi-fiなどを利用
〇 なりすまし、海外プロキシサーバ経由の投稿
2-2.投稿者が特定するまでに、時間と費用がかかること。
弁護士に依頼するとしても、時間と費用がかかります。それで、特定に成功すればよいのですが、2-1の事情から特定に成功せず、弁護士費用が無駄になったというケースもあります。個別具体的な事情にもよりますが、「投稿者特定まで」に弁護士費用だけでも高額なものになります。その後、損害賠償請求など投稿者に対して法的制裁を求める場合、別途費用が必要になります。
2-3.仮に特定したとしても、費用回収ができるかどうかわからない。
仮に特定が成功したとして、そこがスタートラインです。そこから、損害賠償請求を行うわけですが、そもそも投稿者が無資力であった場合、最終的な費用回収は困難です。われわれ弁護士は最終的な回収可能性まで考えて法的手続を検討します。具体的には、相手方の不動産、預貯金、給料などの財産を調べ、回収見込みがない場合(強制執行が困難な場合)は、弁護士費用すら回収できないことを伝えて、受任を断ることもあります。しかし、インターネット上の被害の場合、そもそも相手方が特定できていないので、調査のしようがありません。つまり、多額の費用を投じて相手を特定した(さらには勝訴した)はいいけれども、相手にお金がないので泣き寝入りといったこともあるわけです。
※なお、2020年4月施行の民事執行法の改正によって、より充実した財産調査・開示が可能になりました。詳しくは、法務省のページをご覧ください。
2-4.採算度外視でも、無意味に終わることもある。
2-1~2-3の説明で、多くの相談者は、発信者情報開示を断念されます。しかし、「お金はどうでもいい、とにかく犯人を懲らしめたい」という相談者もたまにいらゃっしゃいます。まず、単に溜飲を下げる目的の訴訟について、ご依頼をお断りすることがあります。仮に受任したとしても、特定ができなければ溜飲を下げるも何もないですし、特定したとしても、投稿者が無資力で「好きにしろ」と開き直られれば、どうしようもありません。そのように考えると、依頼者の方の溜飲を下げるという目的も果たされないことがあるということです。
2-5.さらなる炎上の可能性も。
仮に、犯人を特定したとしても、別の誰かが誹謗中傷的な投稿をすることもあります。その都度法的措置を採ることは、費用や時間、手間の面から考えても、非現実的です。また、炎上に対して法的措置を行ったことで、さらに炎上したケースもあります。発信者開示請求をはじめ、ネット上の誹謗中傷に対する法的措置が、さらなる被害を拡大させることにもなりえまます。
警察は動くのか
発信者情報開示請求には上記のような問題点があることから、民事手続ではなく刑事手続、すなわち警察に通報するという方法は採れないか問題となります。もちろん、警察を動かすことそれ自体は特に費用は不要なので(せいぜい交通費程度)、警察に相談に行かれたというご相談者の方も少なくありません。
理論上は、犯人が特定できていない状態でも、被害届の提出や告訴をすることは可能です(被害届と告訴の違いはここでは省略します)。しかし、現実はなかなか厳しく、少なくとも犯人特定に至っていない段階で、警察が正式に被害届や告訴を受け付けるといったことは多くありません。
もっとも、弁護士が代理人として選任されているケースかつ犯人が特定されていれば、警察との折衝の上で、正式に告訴として受理されることが多いです。ウィステリア・バンデル法律事務所でも、告訴受理された事件を多く取り扱っています。
ネット上の誹謗中傷・炎上などについて、弁護士の選び方
「ネットに強い弁護士」などとして発信者情報開示請求の説明をしている法律事務所や弁護士のサイトがたくさんあります。もちろん、相談・依頼すること自体はまったく問題はありません。しかし、特定成功率の現状や、執行可能性のリスクを説明せずに、安易に発信者情報開示をすすめる弁護士には依頼しないほうが賢明です。ネットに強い弁護士であっても、必ず特定できるわけではありません。また、特定成功事例が豊富でも、「あなたの事案で」特定できるとは限りません。むしろ、優秀な弁護士ほど、失敗の可能性や、それにともなう様々なリスクを丁寧に説明します。
つまり、費用や失敗のリスクを説明せずに、安易に「特定できる」などという弁護士は、避けるべきかと考えます。